 少し前、そうGWのツーリングに出る前までは、灯油バーナーいわゆる灯油を燃料とするストーブには、 「灯油か。今のオレには関係ないかなぁ」なんて思っていたのだが…
少し前、そうGWのツーリングに出る前までは、灯油バーナーいわゆる灯油を燃料とするストーブには、 「灯油か。今のオレには関係ないかなぁ」なんて思っていたのだが…
実際に目の前で実演されると欲しくなってくるものだね。メインに使っているOptimus 123RはそのままREBELでのツーリングに使うとしても、セカンドバイクのイーハトーブで旅に出るときは出来るだけガソリンを節約していきたい。
何せ全部で4.5L、リザーブに入る時点で100km~130kmぐらいしか走ることが出来ないのだから。
新ストーブが届いた
そんな訳で灯油のパワーを見せつけられた現在、私の手元には何故か別体式の新ストーブが…w
購入してみたのはPRIMUSのP-GR-VF、ガソリンと灯油(ケロシン)の2Wayな使い方が可能なヤツである。
購入直後はガソリン用にセットアップされているので、ケロシン用のアダプタ(ジェット)に早速交換して、エルゴポンプを燃料ボトルに差込んで運用開始へとなだれ込む。
と、ここで問題発生。手持ちのMSRボトルではポンプ部分をねじ込むことが出来なかった。どうやら、エルゴポンプのネジが斜めに切ってあるので、細身のボトルでは先っぽがつっかえてしまって差し込むことが出来ないのである。
しょうがないので、PRIMUS推奨のLAKENボトルを追加購入となった。
ボトル容量は0.6Lと1Lがあるが、ここは1Lを選択。ケロシンで使う場合、頻繁に点火と消火を繰り返すのではなく一度点けたら使わないときは種火(弱火)にするなどして、ちびちびと燃やし続けた方が良いようだ。これは、ケロシンの引火しにくいという性質に基づくもので、
- プレヒートに使うアルコールやベンジンを節約したほうがいい
- プレヒートの際に出る煤をなるだけ出さない
という話らしい。
ずっと点火しているのなら燃料ボトルは大きいほうがいいだろうという事で上の結論になったのだが、ガソリンで使うのであれば0.6Lでも問題なく、好みに応じて使い分けるのがいいだろう。
主な内容物
主な内容物を書いてみる。下の他に説明書はもちろん付いている
- ストーブ本体
- エルゴポンプ
- ウィンドスクリーン
- ヒートリフレクター
- メンテナンスキット(レンチ、替パッキン他)
- 収納袋
早速展開
 フル装備で展開させてみたのが右の写真だ。
フル装備で展開させてみたのが右の写真だ。
ウィンドスクリーンとヒートリフレクターについては薄い金属板で出来ており、結構グネグネと曲がる。しかし、何回も使っていると金属疲労で破断するのは目に見えている。
ウィンドスクリーンについては金属端の処理が甘いところがあり、展開・収納時に怪我をする可能性がある(というか私は尖った部分でちょこっと指を刺してしまった…痛いorz)。
また、ヒートリフレクターについても平らに展開できるわけではないので、この上にストーブを置くとかえってぐらついてしまってせっかくの安定性がスポイルされるように感じる(下がふかふかの芝であれば使えるかもしれないが…)。
なので、この二つはあくまで緊急措置用と考えるほうがよく、さっさと正規のものを購入してみるのがいいかとおもう。ヒートリフレクターの代替案に関してはこの後に書いてみよう。
プレヒートについて
ここで、プレヒートについて述べてみる。ガソリンバーナーであれば
1.ポンピング
2.栓を捻って少し燃料を出す
3.ライターで点火してプレヒート
4.本式運用
という手順を踏み、実際この説明書にもこの通り記載されているが、ケロシンが燃料の場合は手順を工夫したほうが良いようだ。
手順を変えるのは2と3の部分。この部分を「アルコールもしくはベンジンなどで、プレヒートする」に変更する。
ここを強引にケロシンでプレヒートさせようとすると、物凄い量のススがでるのでお勧めしない(私は一度やってしまったが…実体験)。
ここで、プレヒートを念入りにやっておくのが上手くいくコツ、らしい。
プレヒートについて色々工夫してみたところ、バーナー部と下の土台部の隙間にベンジンを滴下してプレヒートをするのが、今のところいいようだ。
この辺は既に活用している人の話が聞きたいところである。
使用感
炎さえ上がってしまえばこっちのもの。ここからは使用感について…
気になる火力については、やはり123Rよりも強い。沸騰させる時間がかなり短くなっているような印象を受ける(実際に計っているわけではないが)。
まあ、これは123Rの倍もの出力があるので当然といえば当然。目で見る限りではそう変わらないように見えるんだけどねぇ。
また、レギュラーガソリンよりも赤い炎が出やすく、調理の際に周りが明るくなるのはいいのだが、コッヘルには大量のススが…w
これについては精製したケロシンを使えばいいのだろうが、そうなると運用コストの安さがなくなってしまうので、これについては目をつぶるしかない。1L弱で70円しない燃料代はかなり魅力的だからねぇ。
それから注目すべきは静かな燃焼音。123Rよりの1/2ぐらいに聞こえる。これなら周りに気を使わずにすむね。
後気づいた事として、風に対して炎が消えにくいような印象を受けた。これも123Rと比較しての話だが、我が家の風吹き荒れるベランダで使っていても火は消えない!
これは自作オイルランタンにケロシンを使ったときにも感じたことなので、ケロシン自体そういう特徴があるのだろう。
まとめ
話を総合すると、点火まではちょっとガソリンよりも苦労するが、炎さえ上がれば快適に使えそうな印象を受けた。
これからイーハトーブで旅をする際には必ず携行するようになるだろう。
おまけ
 一番上の写真の真ん中にあるもの、これは100均ショップで買った鍋フタである。
一番上の写真の真ん中にあるもの、これは100均ショップで買った鍋フタである。
最近はコッヘルシステムの変更もあって活躍の場が無かったのだが、鍋つまみを外して右の写真のようにセットすれば、あっという間にヒートリフレクターにw
純正とは違ってストーブの足がはみ出てしまうが、重要な部分はカバーしている。更に凹んだ部分に水を張っておけばいい感じに熱を逃がしてくれる…かも?
購入場所
 PRIMUS P-GR-VF グラビティ・マルチリキッドフューエル・ストーブ
PRIMUS P-GR-VF グラビティ・マルチリキッドフューエル・ストーブ
今回P-GR-VFストーブはI.S.MART楽天店にて購入した。
商品の他にイワタニプリムスとドイターのカタログまで添付してもらって非常に有難かったことを書いておこう。
(2009.05.25追加)
I.S.MARTでは取扱いが無くなっていたようなのでAmazonをリンクに追加した。管理人が購入した時よりも全体的に値段が少し上がっているような。
PRIMUS(プリムス) グラビティ・マルチリキッドフューエル・ストーブ P-GR-VF

それから灯油(ケロシン)で使う場合はポンプ部〜ホース部をつなぐ箇所にあるOリングの寿命が短くなるかもしれない。交換部品についてはこちらのP-GR-VF用Oリングを頼んでみた記事を参考にされたし。
 Snugpak(スナグパック) トラベルパック・ライト
Snugpak(スナグパック) トラベルパック・ライト

 PRIMUS P-GR-VF グラビティ・マルチリキッドフューエル・ストーブ
PRIMUS P-GR-VF グラビティ・マルチリキッドフューエル・ストーブ

 GENTOS リゲルヘッドライト GTR-731H
GENTOS リゲルヘッドライト GTR-731H 気になるサイズ
気になるサイズ

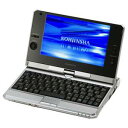
 少し前(と言っても一ヶ月ぐらい前になるのだが…)にゴアウィンドストッパーが割合安価で購入できそうな事を
少し前(と言っても一ヶ月ぐらい前になるのだが…)にゴアウィンドストッパーが割合安価で購入できそうな事を